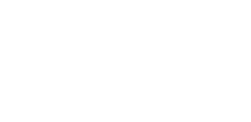初めまして、新2年DLの松永凌です。私は受験生時代、最後のオープン模試でE判定を取ってしまいした。そんな私でも、共通テスト後の勉強を通じて、2次試験を突破し合格することができました。
この時期はおそらく学校もほとんどなく、勉強の時間は十二分にあると思います。だからこそ、今回は2次試験直前期の今、本番に向けどのように勉強していたのか、当時の勉強方法などをお伝えします。このブログが皆様のご参考になれば幸いです。
まず、どの教科にも共通して言えることですが、僕はこの時期から全ての教科内での単元ごとに時間を測り、大まかな時間配分を決めて、それに合わせて過去問を解いていました。何回か過去問を解いていく中で自分にあった時間配分がわかってくると思います。これをすることで「本番で時間をかけすぎた/たりなかった」などのトラブルを最小限に抑えることができます。ここからは教科ごとの勉強法を紹介していきます。
・英語
社会学部はなんといっても英語の配点が多いのはご存じかと思います。そして、一橋の英語の問題形式は常に変動するため対策もしづらいかと思います。私も受験の前年まで超長文、写真描写の英作文が続いていましたが、本番では中文2題と自由英作文が出題されて、試験中にかなり動揺したのを覚えています。
ここで重要なのはまず英語の基本をジャンルごとに、例えば、英単語や文法、解釈、長文読解などの全てのジャンルを一定のレベルまで上げておくことが大切です。これができていれば、過去問だけの問題を演習していると解けないような問題でも柔軟できます。したがって少しでも苦手な単元がある場合はなるべくその演習回数や接触回数を増やしてください。
そして最後に、私自身も行っていて効果があったのは、とにかく「英語に触れる」ことです。この時期、私はスマホの言語設定は英語にし、昼食や入浴時、通学時間には英語のリスニングやシャドーイングをしていました。日本語を第一言語として常に接触するわれわれは「日本語」を受験科目のように勉強せずともスラスラと読み書き聞きができています。ならば、英語も第一言語のように触れ続けることでそれに近しい状態にすることでスムーズに問題を解くことができます。
・社会
英語の次に配点が高い社会科目ですが、その難易度は言わずもがなです。私は世界史選択でしたが、世界史が得意かつ好きだったこともあり、かなりの量勉強をしていました。その中でも効果があったと思うものを紹介します。
まずは「過去問演習」です。一橋の社会は過去問からの類似問題が多く出題されます。したがって過去問の研究は必須です。しかし過去問からの類似問題と言っても数年のスパンでの類似問題は基本的に出ず、数十年前の過去問から出題されることが多いです。したがってとにかく古い問題まで掘り下げることが大事です。私は過去問は40年近く目を通しました。とはいっても30数年前のものなどは現在の教科書の範囲外であることも多く、かつそこまでの演習をする時間もないかと思います。ですので回答や解説を教科書や参考書のように読み込むのがおすすめです。
そして次は「教科書(の頻出範囲)を丸暗記する」ことです。教科書の文は簡潔かつ的確であり、論述には最高の材料です。私は基本的に教科書の文をある程度覚えて、それをそのまま論述演習などで書いていました。自分で文章を創るのは難しく、時間がかかるうえに安定しません。直前まで教科書を読み込みましょう。
・数学
私にとって、そして恐らく社会学部志望の大半が苦手とする数学ですが、ここでは1つ重要なことをお伝えします。結論から申し上げますと、私は「数学のおかげで合格」しました。私は受験生の頃から数学がものすごく苦手であり、過去問演習などでは毎回1完もできず、1,2割が当たり前でした。だから、数学の配点の低い社会学部を志望しました。しかし、さすがにまずいと思い、直前期に数学の過去問演習を以前よりも多く行いました。本番では1完+途中点という手応えでしたが、得点開示を見てみると、数学は5割も取っていました。そして全科目の合計得点的には、数学の点数が普段の1,2割の点数であれば確実に不合格といったものでした。
社会学部は英語と社会の配点が高いため、他の受験生も高いレベルで対策をしてきます。そして国語は基本的に差をつけるのが難しい科目です。それに比べて苦手な人が多く、対策もあまりされない数学では他受験生との点数の差がつきやすいです。だからこそ、直前期では絶対捨てることなく、数学で受かりにいくつもりで勉強することをおすすめします。
・国語
国語は基本的に差は開きづらい科目ですがいくつかポイントを紹介させていただきます。第1問は回答根拠を明確にしながら解くということを意識すると良いと思います。解答・解 説と自分の回答との差を頭の中で常に言語化していくことが大切です。第2問対策としては漢文の基本的な文法や語句の意味を把握しておくことをおすすめします。漢文と共通する部分が非常に多いので必ず確認しておきましょう。そして最後に第3問の要約問題ですが、私は基本的に文章の前から、重要なポイントを抜いて、回答でまとめるといった方法をとっていました。こうすることで要約での事故を大幅に減らすことができます。国語は差が開かない分、安定して、差をつけられない点数を取ることが大切です。
最後に、まず共通テストを乗り越え、ここまで勉強を続けている自分を褒めましょう。誘惑に負けそうになる自分と葛藤し、ここまで走り抜けてきた皆さんにはそれ相応の実力があります。最後に試験に持ち込めるのは筆記用具と「自分」だけです。今までのライバルだった弱い自分を倒して、強い自分で、自信を持って試験に臨んでください。がんばれ!